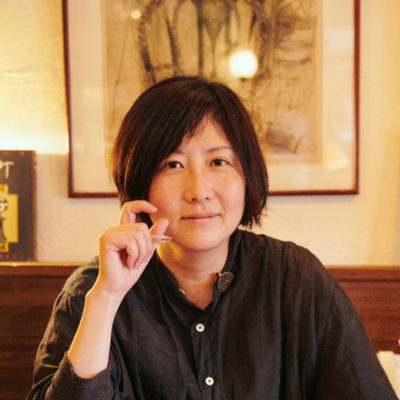Page Index
地域にとって工芸は、この先、いま以上に価値を発揮する、秘めた宝になるのではないだろうか。
自然、風土から育まれた仕事を、いかに文化、産業として継承し昇華させていくか。
新たな視点と手法で実践する人たちがいる。
この連載ではその現場を見にいくとともに、工芸の新たな価値を、つくり手やつなぎ手と考えてみたい。

小林さんを初めて取材したのは、2015年。すでに兵庫県小野市の地場産業である「播州刃物」を海外展開するなどリブランドを軌道にのせていた。プロダクトデザイナーを名乗るが、狭義のデザインではなく、モノの生まれる背景から流通にまで着目し改善策を提案する。
その後、小林さんが小野に「MUJUN Workshop Ono」を立ち上げたのは、2018年。現地を取材してよくわかったのが、高齢化による後継者問題の深刻さだった。
ベテランの鍛冶職人はほとんどが70〜80代で、弟子をとることが難しい。そこで、後継志望者が学べるスタジオを別に用意して、その時もつ技術で製造できる商品を販売しながら、通いで職人に教わりにいくスタイルで、後継者を育てる取り組みだった。
当時、スタジオで働き始めていたのは20代と40代の男性が2人。いま4名に増えているが、当初から続いている一人は5〜6年目の中堅になっている。

この小林さんが、2020年に島根県大田市温泉津に里山を買ったと聞いたときは驚いた。ものづくりの原点に立ち返り、「暮らし、道具、ものづくり」の生態系を構築し直すチャレンジをするという。考え方にはすぐに共感できたが、現実問題として、荒れた山を開墾して野鍛冶の場をつくるという話は気の遠くなるような話に思えた。
里山での暮らしは自然と隣り合わせ。鎌や斧などの道具が多種必要で、鍛冶仕事は欠かせない。かつては村に一人は野鍛冶と呼ばれる職人がいて、道具をあつらえたりメンテナンスしてくれた。日本の山村を訪れるなかでそのことを知ってはいたものの、鍛冶職人は減っていて、なかでも野鍛冶は絶滅危惧種である。
田舎でも人の暮らしはすっかり山や自然の巡りから離れてしまい、量販店には使い捨ての刃物が並ぶ。
そんな現代に、なぜ改めて「里山の再生」なのか。道具をとりまく生態系の結び直しなど、果たしてできるのだろうか? 今回新たに里山の古民家を改修するにあたってクラウドファンディングを始めたという小林さんに、話を聞いた。


小林新也 こばやし しんや
「合同会社シーラカンス食堂 / MUJUN」代表、クリエイティブディレクター・デザイナー、「合同会社里山インストール」代表。播州刃物や播州そろばん、石州和紙、京都の伝統工芸品などの商品、技術、伝え方、意識のイノベーションに携わる。2016年、商品ブランド「MUJUN」をオランダで立ち上げ。2018年に地元の刃物職人の後継者育成を目指して「 MUJUN Workshop Ono 」を設立。2020年から、誰もが職人になれる村「MUJUN Planet」を島根県温泉津につくり始め、2021年には「合同会社里山インストール」を設立。地場産業や地域の営みと暮らしのあり方の未来をデザインしつつ、世界中に販路を持って活動を継続している。
里山にヒントがある「ものづくりの本質」
甲斐かおり
初めて私が温泉津の山を訪れたのは2021年の春でした。小林さんたちが田んぼをつくられていた頃で、その後も何度か見せていただいていますが、毎回どんどん進化していて驚きます。山から木を伐り出してユンボを使って、製材できる環境を整備して…と今4年目ですよね。
小林新也
そうですね。だいぶ進んで、やっと敷地内の古民家を活用しようという段階にきています。まずは山を整備しながら伐った木を木材として使えるようにしてきました。ほかにも山から採った材料でものづくりができる環境を整えたいと思っています。蔵と母屋の台所を鍛冶場にして、それ以外はほかのものづくりができる場にする予定です。小野から一人、鍛冶職人の女性が移住したのを機にクラウドファンディングに挑戦しています。
甲斐かおり
当初「誰もが職人になれる村」をつくりたいと話されていました。始めた理由を、改めて教えていただけないでしょうか。
小林新也
いつか島根で暮らせたらいいなと思っていて、コロナで時間ができた時に、空き家でも探そうと見に来たんです。すると温泉津というまちに、過去に砂鉄から鋼をつくっていた“たたら村”の跡を発見して。その周囲の山には、石垣など里山暮らしの痕跡が残っていました。地元の人が「昔はみんな職人だったけぇな」と言うのを聞いて、それがものづくりの原点かもしれないと感じたんです。
甲斐かおり
必要な道具は自分たちでつくっていたということですよね。生活で使うものは山や田畑から材をとってきて、道具や衣服にしていた。暮らしとものづくりが密接だったんですね。
小林新也
山を管理すると伐り出した木材が燃料にもなるし、ものをつくる原料にもなる。米をつくると、藁灰や籾殻が出て燻炭など鍛冶につかえる素材ができる。暮らしの一部にものづくりがあって、自然にも還元されていくという循環がありました。
甲斐かおり
サステナブルやサーキュラーと言わなくても、衣食住があたりまえに自然のなかにあって、材料を取り過ぎずに再生産されて循環していた。人が自然の営みにあわせて暮らしていたんですね。
小林新也
そうなんです。日本で人が自然から離れて里山暮らしがなくなっていったのはここ100年ぐらいの話ですよね。でも、伝統産業が生まれたのはもっと前。そこにヒントがある気がしました。それでやっと気づいたのが、自然からいただいたもので土地にあった暮らしをして、その風土にあったものづくりをすることが“地場産業”なんだなと。それが伝統になって、伝統産業や伝統工芸と呼ばれるようになっていったにすぎない。
甲斐かおり
はじめにその話を聞いたとき、私もちょうど地域文化のことを書く意味を考えていて「地域の暮らしには風土が切り離せない。風土が生業や文化や環境すべての土台にある」ってことにたどり着いた時期で、すごく共感したのを覚えています。懐古趣味ではなく、この先を考える上で地域の文化に目を向けるのが大事だなと思うようになりました。
小林新也
そうですよね。でも今のものづくりはそこから離れてしまっている。経済主体になって生産性を追い求めて、同じことをひたすら繰り返してものづくりする人が職人という認識になっている。もともと職人は、生活のなかでより少量多品種をつくっていたんじゃないかなと思います。そこで僕、土地を買ったんです、温泉津の里山を。ここならまだ間に合う。すごい可能性があるなと思って。


産地の厳しい現状。職人が消えていく不安
甲斐かおり
でもいま現実には人が里山からどんどん離れてしまっている状況ですよね。それをゼロからつくり直そうとすることに、尊さを感じながらも、果てしない行為のようにも感じます。人が里山とものづくりの関係を体験できる、象徴的な場をつくるイメージなのでしょうか。
小林新也
この里山再生にはもう一つ、すごく現実的な理由があって。このままいくと、自分たちが関与できない理由で、ものづくりができない世の中になっていくという切実な危機感があります。すでに、産業規模のものづくりのシステムは成り立っていない。産業構造のいびつさや高齢化で、いくところまでいってしまったと感じています。なので、いったんもう諦めてやり直すほうが早いんじゃないかと。
量産型のシステムを、それこそ甲斐さんの本の“ほどよい量”じゃないですが、そこに合わせていくより、ゼロベースでしくみを作り直して、ほどよい量を探るほうがやりやすいんじゃないかって話です。
甲斐かおり
それでも地元の小野では、2018年に播州刃物の後継者を育成するためのスタジオを立ち上げて、いまも3〜4名はそこで働いているわけですよね?
小林新也
はい。そのうち一人は、すでに総火造鍛造で盆栽バサミをつくれるところまできています。でもいくら優秀な後継者が育っても、ものづくりの世界は材料や道具が生態系のようにつながっていて、どこか一部でも欠けると、連鎖的に総崩れになってしまうんですね。
甲斐かおり
具体的には、何が起きているんですか。
小林新也
第一に、原料が手に入らなくなりつつあります。最近は「利器材」という、鉄と鋼をあらかじめくっつけた板材を、プレスで抜いて削る手法で刃物をつくる鍛冶屋も多いのですが、小野の利器材屋が一軒廃業したために、10軒ほどの鍛冶屋が連鎖的に廃業しました。需要はあるのに、利器材をつかったものづくりが強制終了したんです。
甲斐かおり
ほかの産地から利器材を仕入れる選択肢はなかったんですか?
小林新也
鍛冶屋が何軒かまとまって仕入れるなら売ってくれるところはあったかもしれませんが、皆さん廃業されてしまって。80代の方も多いので、ごく自然に引退される形で。残すは、完全手づくりの総火造鍛造ができる鍛冶屋です。
そちらは約10年前から後継者をなんとかしようと働きかけてきて、いま握り鋏は、世界で一人の水池長弥さん(80歳)が2015年から弟子を取ったおかげで、寺崎研志さん(44歳)へと引き継がれています。たった一人から一人への後継ですが、もしこの働きかけをしていなかったら今頃、握り鋏も生産終了になっていたはずです。
もう一つがうちの「MUJUN Workshop Ono」の取り組み。弟子入りが難しいなら近くでトレーニングできる場所をつくろうとしてきました。(詳細はこちらより)でも、その総火造鍛造の原料である高炭素鋼(株式会社日立金属安来製作所・現プロテリアル安来製作所の白紙)も、近く手に入らなくなるかもしれないという噂があります。




甲斐かおり
使う人が減れば、原料も売られなくなるという原理ですよね。
小林新也
それもありますが、高齢化など理由はさまざまです。利器材屋が廃業したのは機械が壊れたからで、需要がなくなったからじゃないですし。ただ共通しているのは自分たちの関与できない理由で、原料や道具が手に入らなくなるってことです。
甲斐かおり
それで、廃業された鍛冶屋さんから、機械や道具も集めているんですね。
小林新也
そう。二つ目には道具がなくなっていくという話。放っておくと、廃業したあと、今はもうつくられていない貴重な機械がスクラップされて鉄屑になっちゃうんですよ。いま同じ機能の機械を新しく仕入れると高額な投資になります。職人が独立する際にそれだけの投資をするのは現実的じゃない。
甲斐かおり
後継者がいたとしても、満足にものづくりを続けていける環境ではなくなっているということですね。
小林新也
そうです。彼らの将来は今のままでは報われない。産地ではいまだに問屋の力が強くて、水池さんの後継者である寺崎さんに、問屋がもってくる仕事は量産型の利益の低い仕事です。特殊な刃物のオーダーも来ているので、そうした付加価値の高い仕事に時間を割きたいはずなんですが、問屋との関係性も大事にせざるをえない。量産型の産業構造が変わらない限り、独立しても職人が報われることはないんだなと。
甲斐かおり
そうした背景がすべてこの里山再生につながっていると。
小林新也
世の中から職人が消えていく不安が拭えないんです。里山で原点に向き合って初めて安心できるんじゃないかなと思う。今は安心できないんですよ。




原料の鋼(はがね)をつくる「たたらキャンプ」を予定
甲斐かおり
ということは、原料から自分たちでつくってしまおうと?
小林新也
そうです。温泉津に着目した一番の理由は、砂鉄が大量に採れることです。もともと“たたら”の場所なので。鋼をつくるには炭も必要ですが、里山から木を切り出して炭もつくろうと思っています。
甲斐かおり
また気の遠くなる話にも聞こえますが、Workshop Onoもはじめは遠回りに思えたけれど、すでに6年経って、中堅の職人さんが育っていると伺うと、少しずつでも着実にやっていけば現実になっていくのだと思わせられます。
小林新也
原料づくりは、まぁ最初は年に一度くらいのペースで。この夏初めて「たたらキャンプ」を計画しています。一斗缶を4つ重ねたくらいの規模感ですが、砂浜で、砂鉄と炭を交互に入れて燃やしていくと、ケラというものができて、その中に鋼が含まれます。刀一振り分くらいは鋼が生成できるので、ハサミなどに使うには相当な本数分採れるのではないかなと思っています。
甲斐かおり
すでに計画があるんですね。
小林新也
ひたすら暑くてきつい作業なので、暑くなったらすぐ海に飛び込めるように海のそばでバーベキューしながら、楽しくみんなでイベント的に開催できるといいなと思っています。このときは小野のメンバーも呼んで一緒に。
甲斐かおり
鋼に限らず、里山から木や竹など材を得ながら、暮らしとものづくりを循環させていく実験的な場をつくりたいんですね。
小林新也
そうです。木材を乾燥させて製材加工する環境はすでに整ったので、家を建てたい人は建てられますし、竹で何かしてみたい人がいたらできますし。



誰もが職人になれるはず
甲斐かおり
最初にお話を伺ったときは、もう少しプロの職人が集うビレッジをイメージしていましたが、誰もが山やものづくりにひろく関われる場にしていきたいんですね。
小林新也
要は、職人になる人を増やしたいんです。もっと気軽に、みんなものづくりしたらええやんって思うわけです。そんなに難しいことじゃない。職人をすごいと思いすぎているけど、みんな自分でつくれるよって。手を動かす経験が圧倒的に足りていないと思います。だから今何でもお金で買うしかないわけじゃないですか。
甲斐かおり
まずは気軽にものづくりできる場をということですね。すると、宿泊機能や、教育的な機能もある体験施設のような場になっていくのでしょうか。
小林新也
それもあります。まずは里山の暮らしやものづくりに興味のある人たちに、ひらかれた場であることが重要だと思っています。来たら誰でも山に入れる。みんな一度は山でものづくりの体験をした方がいいと思っていて。
たとえばデザイナーと呼ばれる人たち、この世にものを生み出す責任を負っている人たちは、山に入るのを必須科目にした方がいい。デザインの教育は都会を向いていて、キャドの使い方や、イラストレーターの使い方は教えてくれるけど、刃物の研ぎ形なんて誰も教えてくれない。
甲斐かおり
すべての道具を自給するわけじゃないにしても、自分の手でつくってみたり、つくるという地点に立ってみるのが大事という話ですよね。食べものも同じで、プロの農家のようにはいかないけど、素人ながら野菜を育てると見えてくることがたくさんあります。
そうした手を動かす経験、身体感覚としてものづくりに向き合うことが圧倒的に足りない。でも、やってみたくても周りにそうした環境がないとハードルが高い。
小林新也
はい、気軽に道具のことを相談したかったらここへ来たら野鍛冶がいるよと。それに、国内外問わず、いろんな人が出入りする場だといいなと思っています。アーティストインレジデンスで毎年アーティストを受け入れていく予定ですが、海外から来たクリエイターと新しいチャレンジをしていきたい。バックグラウンドの異なる人たちが集まって、いろんなアイディアが生まれる。そこに興味があるんですよね。



現代の生活に里山の要素を取り入れられるブランドを
甲斐かおり
今の時点でビジネスとして考えられていることはありますか?
小林新也
嘘のない、しっかりしたブランドをつくりたいなと思っています。そこは自分の本分のプロダクトデザインを通して。嘘がないってのは、量産しても環境負荷をかけないとか、つくり続けられるという意味です。
今試作しているのは、囲炉裏です。薪ストーブと囲炉裏のあいのこのような、現代の生活にも里山の要素をインストールできる商品をつくっていきたいと思っています。囲炉裏のまわりには、鍛冶の道具も多く必要になるので。
甲斐かおり
いいですね。昔のままの囲炉裏ではなくて、現代の暮らしにも、すっとおさまるようなおしゃれなものがあるとすごくいいですね。
小林新也
そうしたブランドが確立したら、ショップの機能ももつことになるかもしれない。温泉津を観光的に盛り上げたいというより、里山でインパクトのある実験的なことをしていきたいのです。設備というよりプロダクトの感覚で小水力発電できる装置の実験も始めています。
甲斐かおり
現代の生活に里山の要素を取り入れられる形にしていけるといいですよね。
小林新也
まさに。だから温泉津のほうの社名は「里山インストール」なんです。テクノロジーを否定しているわけでは全くなくて、むしろ最先端のことを取り入れていきたい。



工芸と自然の関係を問い直す必要があるのでは
甲斐かおり
ずっとものづくりの現場を情熱をもって見てこられた小林さんが、今のシステムにはもう限界がきていて、いったん諦めたという話は衝撃です。だからこそ、遠回りに見えても、いったん質が落ちても、原料から自給できるしくみをつくり直そうとしていると。鍛冶に限らずほかの分野でも、原料が足りない、道具がないという話を耳にします。やむをえず原料から育て始めている職人さんも出てきていますよね。和紙も、漆も、藍も、取材すると原料や道具の話になりました。
小林新也
量産型のしくみは、もう成り立っていないですよね。次々にいろんなものがなくなっていっている。ある日気づいたら原料がない、道具がないで突然ものづくりができなくなるなんて、普通に想像できます。それを阻止するには、自分たちで、今のうちから手を打つほかに方法がないって話ですね。
僕の周りでは、播州刃物もそろばんも播州織も似たような状況で、基本的には成立していない。林業もそうですよね。
甲斐かおり
補助金なしには成り立たないという面では同じかもしれませんね。まだ間に合う引き継げるものは引き継ぎながら、新たにつくり直すつもりでってことですね。
一方で、職人が数をこなして洗練されたレベルの高い品をつくる世界と、誰でも自由にものづくりをする世界があるとしたら、前者が美的要素まで兼ね備えて工芸と呼ばれるようになった歴史があるわけですよね。それについては、どう思われますか?
小林新也
それはもちろん、数をこなしてきた人だからこそたどり着ける境地が、絶対あります。訓練なので。1つのものづくりを、ずっと続けることは誰にでもできることじゃない。そこにこれまでの職人の凄さがあるというか。刃物のベテラン職人は、短時間で国宝級のすごい精度のものをつくりますから。
でも一方で、それが職人像だと思っている時点で、自分たちにも量産の概念が染みついているんだなとも思うんです。
甲斐かおり
同じものを何百個も何十個もつくるのは、日常で使うだけじゃなく、流通させる時代に適応して始まったってことですね。
小林新也
そう、もともとは、もっと少量多品種のものを、地域に根ざしてつくっていたはずです。この国土のほとんどは山林で四季があって、日本人はときに猛威を振るう自然と向き合いながら生きてきた。うまく自然を活かして生活でつかう道具と、自然に対して畏敬を表すためにつくった神社など宗教的なものづくりの二つの方向性で、工芸が磨かれていったと思うんです。
なので「工芸職人」とは、「自然を活かして自然に生かされる人」を言うんじゃないかと思うようになりました。
甲斐かおり
自然界から素材を取ってきて、人が使う形に変えられるスキルのある人。
小林新也
はい。かつそれが自然破壊にもなっていない。自然のサイクルや成長スピードをわかった上で、使っていい量、ほどよい量をわかっている。それはやっぱり、山に入っていないとわからない。今の「伝統工芸士」と呼ばれる人たちのなかで、それができる人はどれだけいるのかなって。
4年間里山と向き合って、僕が今の工芸界というか、分業の進んだ日本のものづくり界に違和感を覚えたのはその点です。その両方を理解できて実践できている人だけが、本当は職人と名乗っていいんじゃないかと思うくらい。職人像を定義し直すべきなんじゃないかなと思います。
甲斐かおり
工芸の本質的なところは、自然との関係性にあるんじゃないかという話ですね。
自然との関係を取り戻すために里山に入って、循環型の暮らしを実感してみるところから始めるのがいいという話にとても共感します。そのための里山再生で、かつ今回の職人向け工房の設立。知ればまず道具の必要性がわかり、木や竹が道具になることも実感としてわかる。
これまでに大勢が里山再生の活動に参加してこられた事実をみても、そこに立ち返る必要性を肌で感じている人が多いのかなと思います。鍛冶やものづくりに限らず、衣食住すべてにつながる原点が里山での暮らしにある。そこからまず始めてみようという話かもしれませんね。
クラウドファンディング:「里山の鍛冶屋から始まる!持続可能なものづくりのための工房」