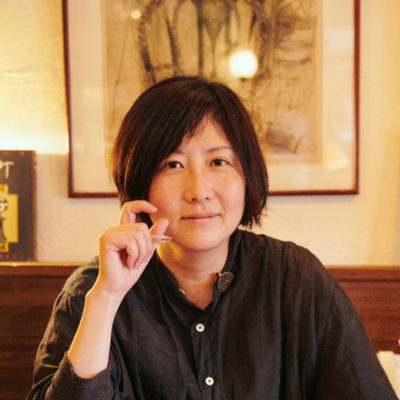Page Index
地方において、工芸はこの先、いま以上に価値を発揮する秘めた宝になると思う。自然、風土から発展した仕事を、どう変換し、文化として昇華させるのか。
新たな視点と手法で実践する人たちがいる。
この連載ではその現場を見にいくとともに、この先、いかに工芸の新たな価値を見出していけるのか、つくり手やつなぎ手と考えてみたい。

佐賀県の名尾地区は、梶の木が豊富に自生することから、和紙の産地となった。いま和紙の原料は品種改良された楮が多いが、梶はその原種である。名尾では最盛期には100軒あった工房が、いまでは一軒のみに。だが最後の一軒という環境が、和紙を自由なものにした。「名尾手すき和紙工房」では梶を育てながら和紙を漉き、クライアントワークも、オリジナルのプロダクトづくりも行い、独自の作品を生み出し続ける。
和紙は伝統工芸品の枠にはおさまらない、見る人に多くのことを感じてもらえる媒介になれるのではないか。七代目の谷口弦さんはそう話した。
名尾和紙の産地へ
朝からの雨で、春の里山はしっとり湿っていた。佐賀県佐賀市大和町名尾地区は干し柿の産地でもあり、山のふもとは柿の樹のみずみずしい若葉に覆われていた。車で進むと、やがて新緑の中に浮かび上がるように「名尾手すき和紙工房」の工房が見えた。
作業場では七代目の谷口弦さんが、次の作品づくりに勤しんでいた。

名尾地区は、紙すきに必要な清らかな水があり、原料となる梶の木が自生していることから、製紙に向いた土地だった。わざわざ植えなくても、あたり一帯にはもともと梶の木が多く自生していた。最盛期には100軒以上の和紙工房があったが、いまでは「名尾手すき和紙工房」のみとなり、谷口さん一家と職人たちが和紙づくりを続けている。
手を休めることなく、谷口さんが話してくれる。
「このあたりでは主に柿や米をつくってきました。でも山じゃないですか。人は増えるのにこれ以上土地がない。困ったなということで、八女から製紙の技術を持ち帰ったのが名尾和紙の始まりと言われています」
名尾和紙には300年以上の歴史がある。まず越前から八女に製紙の技術が伝わり、それを学びに行った職人が地元の名尾に持ち帰り、名尾和紙が始まった。
藩などに推奨されたわけではなく、あくまで自発的に始まった産業のため、原料の調達も売り先も自分たちで開拓するほかなかった。それでも需要があったため、梶の栽培と製紙は盛んになった。
水槽をのぞくと水は限りなく澄んでいた。 「このあたりはいまも水道が通っていないんです。山の水を汲み上げたもので、地下水なのでそんなに冷たくないし、夏も冬も、17〜18度とある程度一定の温度です」


和紙に定まった形はない。「紙はそこにあるだけ」
谷口さんのつくる作品は、工芸というよりアートとして捉えられる作品が多い。家業に入って2年は技術の習得に没頭し、初めて制作したのが「還魂紙」をモチーフにした作品だった。還魂紙とは、鎌倉時代には弔いのために遺灰を紙に漉き込んだものを指し、江戸時代には手すきで再生した紙そのものをそう呼んだ。
初めて雑誌『POPEYE』を紙に漉き込んで以来、落ち葉やTシャツなど、さまざまなものを漉きこみ作品にした。和紙を素材以上のものにしたいとの思いからだった。
その後、編集者やデザイナー仲間とともに立ち上げたのが、アートコレクティブ『KMNR™(カミナリ)』。KMNRから発表した代表的な作品のひとつに「関守石」がある。関守石とは、日本庭園や茶室の露地などで、立ち入り禁止を表すために置かれる結界の石。和紙を塊にして石に見立てた。

そんなふうに試行錯誤をするうちに気づいたことがある。和紙には定まった形がない、ということだった。
「名尾和紙は佐賀県の重要無形文化財指定を受けていますが、無形ということで、香りやお茶に近いと言えるかもしれない。 三角形に切れば三角形になるし、水にさらしておけばいずれ溶けてしまう」
木の繊維を水にといて漉くが、成形や乾かし方次第でペラペラの紙にもなれば、石のような塊にもなる。それはいずれも一時的なあり方で、現象にすぎないという。
「どこまでが梶の木で、どこからが和紙だという境界線も明確ではないですし。自分たちで梶の木を栽培しているので、山からくる養分、水、太陽の光でできていることを知っています。何百年も同じ株から新しい枝が出て、その枝を伐採して紙の原料にするわけで。だから和紙は、太陽でもあり、水でもあり、土でもある。森羅万象なんです」

「山」と思っていたものは「山」ではなかった
紙はそこにあるだけ。いまこの瞬間、その形をとどめている現象にすぎない。リアルにそう思うようになったきっかけがあった。
2021年の大雨による被災だ。
8月12日、九州北部地方では線状降水帯が発生し、多いところで24時間400mmを超える雨となった。谷口さんの自宅や工房は、この雨で甚大な被害を被った。
この時、谷口さんは、自宅が土砂に飲み込まれるその瞬間を、対岸の斜面から見ていたのだそうだ。
「家族では僕だけが消防隊員だったので。家のそばは危険で近づけないし、おまえ上って見てこいと仲間が言ってくれて。向かいの山から家を見ていたんです。さらさらさら…と砂が動く音が聞こえて、すごく静かにさーっと隣の山が砂になって流れてきてがちっと固まったんですよ。混乱していたのもあるけど、すごいものを見たという気持になりました。これって紙と一緒じゃんと。不謹慎かもしれないけど興奮したんです」
「山」だと思っていたものは、その時「山」ではなかった。砂であり、水であり、流れだった。分解されたモノとしての印象が鮮烈に残った。
ずっと「和紙には何かがある」と思い続けてきたが、この経験から「紙に何かがあるんじゃなくて、見る側の心に何かがあって、それが映し出されるだけなのだ」と思うようになった。紙は現象としてそこに存在するだけだと。

「伝統工芸」の枠でくくられる違和感
家業に入る前から、名尾和紙が「伝統工芸品」としてくくられることへの違和感があった。
「自分が和紙をつくる意味ってなんだろうと考えました。次世代につなぐとか、技術を絶やさないとか、美しい紙を追求するだけなら、僕じゃなくてもすでに多くの人がやっている。伝統工芸だから無条件に残さなきゃいけないと言われますが、誰かもう少しその理由を教えてよと思ったんです。工芸を残す価値、意味が何なのか」
大学進学のために家を出て、卒業後は大阪でアパレルの仕事についた。幼い頃から和紙づくりは常にそばにあり、職人さんたちに可愛がられて育ったため、家業にネガティブなイメージはなかった。いつかは戻るのだろうと心のどこかでは思っていたものの、継ぐことに、すぐには意味を見出せなかった。
「確かに伝統工芸っていいものですけど、下駄を履かせてもらっている気もするんです。困り顔をするのが得意で、恵まれているのに『大変です』って顔をしがちというか。伝統工芸じゃなくたって、いまの時代みんな生きていくの大変じゃないですか」

プレゼンテーションが紋切り型だとも感じた。たしかにメディアでも「伝統工芸品」だからこう見せようとする定型に当てはめがちだ。
伝統工芸は切磋琢磨しながら変化し続ける生きている文化というより、作り手にとっても受け手にとっても、閉じ込められる枠になってしまっているのかもしれない。
「自分は、一度も跡を継げと言われたことはないですし、継ぐも継がないも自由でした。でも何の仕事でもそうだと思いますが、一つのことを極めると、そこに法則が見えたり、腑に落ちる瞬間みたいなものがありますよね。それが工芸の世界はとてもわかりやすく継承されていると思ったんです。
だからこそ工芸から導き出される、ものの考え方や捉え方があるんじゃないか。自分がどう世界を見るのか。どう切り取るのか。大げさにいえば、この世の真理をひもとく秘密に近づけるんじゃないかとさえ思ったんです」

技術では江戸時代にかなわない
2021年の豪雨被害により古い工房が使えなくなり、新しい工房と直営店「KAGOYA」が建てられた。被災したのがお盆に近い時期だったこともあり、今では「じいちゃんからのプレゼントだった」と思えるようになった。
新しい工房は広く、自然光が入り職人からも外の世界が見えるよう、窓を大きくとった。できるだけ自然と一体化するなかで、ものが生まれる環境をつくりたかったという。
工房では谷口さんのお父さん、六代目の祐次郎さんが紙を漉いていた。横には歴30年のベテラン職人の女性。わしゃっわしゃっと水を弾く音が響く。

どれほど紙漉きの技術を追求しても、いま一日に漉く枚数は、江戸時代の何百分の一になっている。
「祖父が言っていたのは、いま自分たちのレベルは江戸時代の職人に到底及ばないよと。当時は職人の数も多かったわけですし、一人が一日中何千枚も紙漉きしていた。いまとは桁が違います」
谷口さんはもう一つ、面白い話を聞かせてくれた。
「タイのスコータイに、日本の技術で和紙をつくっている工場があって、見に行ったことがあるんです。楮も育てていて、工場では日に5000枚くらい漉いている。なので職人さんの技術がめっちゃ高いんです。紙を漉いたあと伏せて、トントンとして簀桁からさーっと離す。それは日本からの技術でもなくて、彼らが経験を重ねるうちに編み出した、オリジナルの技だと思うんですね。それを見たとき、もう全然これでいいじゃんと思いました」

“何も描かれていない状態”が和紙の本質
谷口さんの工房の横にはショールームを兼ねたショップが建っており、その入口には和紙の暖簾が揺れている。中へ入ると、天井からさまざまなバリエーションの紙が吊り下げられている。



店奥には「和紙の部屋」がしつらえられており、天候や光によって見え方が変化する。ほんのり青みがかったり、グレー、アイボリーに見えたり。中に居るだけであたたかく和紙に包みこまれるような感覚がある。
店内向かって右手にはクライアントからの依頼でつくったパッケージなどの品。左手には自社のオリジナル商品。名尾では問屋を通して売ることがないため、仕事は直にくる。さまざまなリクエストに応じるうちに、和紙の使い途、幅が広がってきた。

和紙はどんな形のものにでもなれる。
「ティッシュとして使われたり、紙ストローとして吸われたり、用途も変わる。そう考えると紙ってめちゃくちゃポテンシャルが高いんですよね」
そして最近、一つの仮説をもっている。
「どんなモノにも本質があります。機能とも言い換えられますが、たとえばスプーンなら“何かを掬って口に運ぶ”ためにあの形になった。じゃあ和紙の本質は何だと考えると、よく言われるのは、文字を書くこと。昔は木簡と呼ばれる木の板に文字が書かれて、その代わりに和紙が必要とされたと言われます」
だが今は西洋の紙があり、和紙に文字を書く人は少ない。
「そこでもう一つ深いレイヤーで考えてみたんです。そしたら何かを書くためというより、“何も描かれていない状態そのもの”が紙の本質なのではないかと。 そう仮説を立てると、僕たち名尾和紙の職人は『和紙をつくってきた』のではなく『何も描かれてない状態』を漉き続けてきたことになる。そしたらミニマルな世界観が立ち上がって、すごくかっこいいし面白いと思ったのです」

自然がつくる現象が、人の心を映し出す
まだ何ものにもなっていない状態を、和紙を通してつくり続けてきたということだろうか。
「たとえば入口にかかっている和紙の暖簾も、いま風で揺れていますが自らの意思で揺れているわけではないですよね。光も通しますが、和紙が光を通そうと思っているわけではない。あくまで現象で、自然に身を任せてそうなっている」
和紙に意思はないけれど、周りの環境によってそのものが変化する。
「そう。それでも堂々と存在している。その現象から人が感じ取れることはたくさんあるなと思うんです。たとえば人も、自分のシルエットに固執する必要はないし、それだけが自分じゃない。僕たちはつい自分を大きく見せたり、奮い立たせるようなことをしがちですが、自然に任せて堂々としていればいいんじゃないかとか。和紙を通じていろんな捉え方をすると、ポジティブになれたり、見習わなきゃいけないことが見えてくる」

紙が、人から何かを引き出す媒介になるということだろうか。
「紙そのものが必ずしも人を引きつける何かを持っているのではなく、人が紙に自分を映してしまう。紙に魅力があるわけじゃなくて、その紙に魅力を感じる人の心のほうに何かがある。映すのは自分。見る側によって変化するのではないかなと」
谷口さんにとっての和紙とは、他者とコミュニケーションするための、あるいは何かを伝えるための手段であると。
「そう見た方が面白いなと思いました。伝統工芸品として継承されることが本質ではなくて、誰かがそれに感動し続けているから残っていると信じたい。そういう効能が和紙にはあって、効能が役に立つから残すに値すると思えるようになったんです」
それによって作品も変わりましたか?
「変わったと思いますね。必ず“現象”を入れるようになりました。人工的につくる意匠のかっこよさではなくて、自然がつくる現象。たとえば先ほどつくっていた和紙の器も、きれいな形にするには乾くまで放っておく方がいいんです。でもそうなる前に型から外します。紙は濡れて乾燥させるとシワになる。水が抜けるとき、勝手に動くんですよ。それがそのまま形として残る。自分は造形作家じゃないのでそこは『自然にお任せします。どうぞ、乾燥してください』という気持です」
この新作には「かご」と名付けた。ただの容れ物、器として見る人もいるかもしれないし、自然の成した造形、繊維の塊にも見える。

名尾という土地にアンカーを下ろしている感覚
いっぽうで、名尾和紙には名尾和紙である理由がある。土地性。ここで生まれたという事実だ。この場所でなければできないものづくりをどう捉えているのだろう。
「イメージで言うと、船のアンカー、重しですね。アンカーを下ろしておけば漂流しないので、紐を長くすればわりと遠くまで行けちゃう」
何より、名尾には梶の木が繁る。梶からは離れられない。

だからこの先、作品もプロダクトも、名尾という場所をもっと掘り下げたものづくりをしていきたいという。
「この土地をまだしっかり紐解けていない気がするんです。和紙の歴史もせいぜいここ300年ぐらいなので、その前はみんな何やっていたんだろう。なんでこんな山の中に神社があるんだろうとか。土地から導き出されるアイディアでものづくりができると、さらに新しい扉が開きそうな気がしています」
名尾の稲ワラや泥を紙に漉きこむなど、土地のものを素材として作品やプロダクトに活かすのはすでに行ってきた。この先はさらに、土地のものをモチーフとした作品やプロダクトを生み出したいと思っている。
「ここでしかさわれないもの、ここでしか手に入れられないものが一番尊いですから。クライアントワークでも、僕らに依頼がある際は『名尾産でないと』という思いで来てくださる方がほとんどです。その方たちにいい提案をしていくためにも、名尾の自然や歴史、人との関係性の中からしか新しいアイディアは生まれないと思っていて。僕もそういうモノが欲しいと思うんです」

取材協力

名尾手すき和紙
佐賀県佐賀市大和町大字名尾4674‐1
直営店「KAGOYA」
電話:0952-63-0334
営業時間:9:00〜17:00 定休日なし / 正月、盆期間を除く
公式HP:https://naowashi.com/