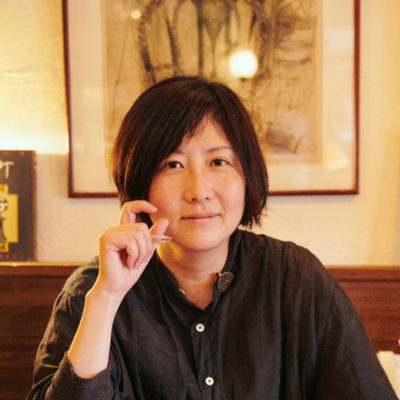Page Index
地域にとって工芸は、この先、いま以上に価値を発揮する、秘めた宝になるのではないだろうか。
自然、風土から育まれた仕事を、いかに文化、産業として継承し昇華させていくか。
新たな視点と手法で実践する人たちがいる。
この連載ではその現場を見にいくとともに、工芸の新たな価値を、つくり手やつなぎ手と考えてみたい。

しんとした小さな工房で、山内ゆうさんは和紙と向き合う。冬は屋内にいても息が白くなるほどの冷たさだ。
しゅっしゅっと霧吹きで水をかけ、ほどよく湿らせた紙の短冊を、石の上でしごいて糸にしていく。ひと月の大半をかけて紙を撚り糸にしたものを、布にする。彼女のそうした静かなものづくりを見ていると、仙人のようにも思えてくる。
山内ゆうさんは、和紙から紙糸をつくり、その糸で紙布を織る作家。 紙布とはどんなものなのか。山内さんはなぜ、山奥の工房で一人紙布を織っているのだろう。島根県の山あいにある工房を訪ねた。

紙布との出会い
島根県邑智郡川本町。前回紹介した石州和紙の産地、三隅町から車で1時間ほどの場所にその工房はある。 山内さんは4年前に川本町へ移住してきた。地域おこし協力隊として3年間の準備期間を経て工房など制作環境を整え、織物作家としての活動を始める。
私が山内さんに出会ったのは、2年前、彼女が協力隊活動の 3年目を迎える年だった。将来に不安はないかと問う私に、彼女は穏やかな口調で固い決意を話してくれた。覚悟が違う。その印象が強く残った。
「やれるかやれないかではなくて、もうやると決めたので。私が形にしてみないことには、どういうものをつくれるのか誰もわからないですから、たくさんつくって、こういうことができますと見せていかなければと思っています」

紙布との出会いは、23歳のときだった。神奈川県横浜市の出身。子どもの頃から布が好きで、短大の芸術科を卒業後は、和裁の学校や、志村ふくみさんの染織学校で絹織物を学ぶ。学校へ行く前に、京都で出会ったのが紙布だった。
「ワークショップで偶然、カナダで紙布織をされている、軽野裕子さんという方にお会いしたんです。軽野さんの糸を見た時に衝撃を受けて。和紙からつくった糸とは思えなかった。それほど細くて美しい糸でした」
ただただ、その糸を美しいと思った。この出会いがその後、山内さんを紙布へと向かわせた。

地元の石州和紙を使って
川本に住み始めて知ったのが、近隣で生産されている石州和紙だった。日本でもっとも強いと言われる和紙は、紙布にするのに最適だった。
「この地域の紙を使いたいなと思って、石州和紙の制作現場を訪ねました。楮(和紙の原料となる植物)の繊維は通常0.8cmほどですが、石州和紙で使われるものは1cmと長く、表皮と呼ばれる部分を残したまま紙にするので強度があって、紙布に向いているんです」
「石州和紙から紙糸をつくり、その糸で紙布を織る」 いつしか、それが山内さんの作品の基本になる。
西田和紙工房の西田さんは、山内さんが紙布をつくろうとしていることを知って「頑張りな」「この和紙でよければ、つくってみて」と背中を押してくれた一人だった。紙布にする材は、西田和紙工房にいつも在庫がストックしてある定番の紙を仕入れる。


紙布とは何か?
紙布とは、和紙を細くカットし、こより状に撚って糸にしたもので織る布のことを言う。
今でこそ珍しいが、江戸時代には身近にある和紙で布ができるというので、多くが自家製でつくられた。和紙が身近にある産地ではとくに、“土着のものづくり”といえるものだった。
まだ日本で木綿が普及していなかった時代には、麻をはじめ、さまざまな植物が糸や布の原料として用いられた。和紙の原料である楮 もその一つで、紙布とは別に、楮の繊維をそのまま布にした「木綿」と呼ばれる布も存在する。だがゴワゴワとしていて肌当たりが紙布ほど柔らかくない。
一度繊維を紙にしてそれを再び糸にする紙布は、二度手間のようでもあるが、現代の木綿 と風合いが似てあたたかく、肌触りもよく、軽くて丈夫であるため、夏の衣料として重宝された。
実際、山内さんに見せてもらった紙布の風合いは柔らかく、木綿よりもハリがあった。
紙布はあくまで家庭で織って自家消費するものであって、市場に出回るものではなかったが、宮城県の白石紙布だけは、武士が着る品格のある布として献上品に用いられた。木綿の栽培に不適な寒冷地では、自家製できる、大切な防寒の衣料でもあったのだ。

「糸をつくるのが一番大変」
和紙づくりも体力と根気のいる大変な仕事だけれど、紙布づくりはさらに細やかな仕事の続く、根気のいる仕事だ。
ひと月半をかけて、帯一本がようやく仕上がる。帯一本を織るために、畳3分の1ほどの大きさの和紙を50枚近く使う。和紙1枚分を糸にするのに6時間かかるため、50枚を糸にするには300時間がかかる。昼夜問わず作業を続けても約1ヶ月だ。



ひと月かけて糸にしたものを、織って布にするには2〜3日から2週間ほど。つまり、紙布をつくる工程の大半は糸づくりになる。
「糸をつくる工程が一番大変で。そこまで終わったら完成間近です。織るのは、模様にもよるんですけど、2〜3日もあればできます」
そうは言っても、織りの作業もそれはそれで大変で、模様を設計して機織り機に経糸を張り、緯糸をくぐらせてトントンと筬で寄せるという作業を繰り返す。

地味な作業を繰り返すこの仕事を、山内さんはこう表現した。
「料理にたとえるとひたすら美味しい白めしを炊くような仕事です(笑)。中華やイタリアン、スイーツなど目新しいものをつくるのとは違って、ただ地道に白めしを炊く。それもじんわり美味しい白めしを目指すような」
どこまで、その素材が成りたい形に近づけられるか
織り上がった紙布を何枚か見せてもらった。未晒しの紙を使った、うっすら経糸と緯糸が感じられる美しい生成りの反物。もう一枚は、ランダムに黄色や藍色が入った、翠の絣のように見える織物。


けして派手ではないのに、素材から上品で涼しげな感じが伝わってくる。麻のようでもある。
生成りの帯《朧》は、2020年の島根県総合美術展で金賞を受賞。さらに翌年、こちらは木綿だが、「木綿緯絣帯地《南国花鳥図》」が全国伝統的工芸品公募展全国商工会連合会会長賞を受賞した。 県展では、2021年2022年とも連続して、紙布の帯が銀賞金賞を受賞している。

数々の受賞に関して「おめでとうございます」と山内さんに告げると、「ありがとうございます。でもまだまだで…」と濁すような言葉が返ってきた。
「ありがたいことではあるのですが、自分としてはまだ目指す域に達していない、作品に納得できていない気持ちも強くあって。
糸から自分でつくるから、愛おしくて美しいなという気持ちはもちろんあります。でも、この和紙がなりたい形にはまだなっていないんじゃないかって」
圧倒的に自分の中にデータが足りないのだという。引き出しが増えれば、「こうしたらこう見えるという予測が立てられて、さまざまな組み合わせができるようになると思う」と話す。

紙布を織る上でめざすところがあるのですかと聞いてみた。 しばらく考えて、山内さんは「自分の意思や自我が先行しすぎていないもの」と言った。
「自分がコントロールするのではなくて、あるべきものがあるところにある。その素材がなりたい形になっていると感じられるようなもの。すべてにおいて無理がないというか」

渡邊紗彌加さんという織の作家さんの展示会へ行った時にはボロボロ泣いてしまったのだという。
「染めた糸に命が宿っていると感じたんです。自分の糸はまだそうなっていない。
楮という植物の命、草木染めの植物の命、そして私自身の命も宿るような。そういうものがいつかできたらいいなと思います。そういう域に辿り着けたら」
手の内の紙に向き合い、寄り添うように糸を撚り、織り続ける。過去から継がれてきた土着のものづくりである「紙布」に、山内さんの手で新たな命が吹き込まれる。