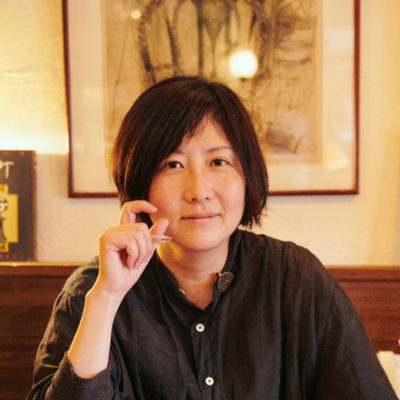Page Index
地域にとって工芸は、この先、いま以上に価値を発揮する、秘めた宝になるのではないだろうか。
自然、風土から育まれた仕事を、いかに文化、産業として継承し昇華させていくか。
新たな視点と手法で実践する人たちがいる。
この連載ではその現場を見にいくとともに、工芸の新たな価値を、つくり手やつなぎ手と考えてみたい。

まるでパンを焼く小麦粉をこねるように、佐々木りつ子さんはやきものの土をこねる。慣れた手つきで黄土色の塊をリズミカルに押すと、わしゃっ、わしゃっ、わしゃっと湿った土の音が響いた。
器をつくる仕事は、日々畑に出て、自分や家族が食べる穀物や野菜を育てるなど、佐々木さんにとっては生活のための仕事の一環にあたる。育てた小麦でパンを焼き、味噌などの発酵食品もつくる。陶芸の作業場も自宅の一角にあり、生活の一部に器づくりがあるようだった。

暮らしの一部にある陶芸
広島県と島根県の間に横たわる中国山地のふもと。安芸高田市高宮町川根という小さな集落に佐々木さんの家はある。田畑仕事をしながら、「朴禾」の屋号で、マグカップやお皿などの器、花瓶、植木鉢などをつくり、展示会やインターネットで販売する仕事をしている。
ここで暮らすようになって、生活に時間の比重をおくようになった。
「以前は今よりずっと陶芸の仕事に時間も労力もかけていました。今の10倍くらいは。数をつくればそのぶん上達するし、そのスタイルをずっと続ける作家さんもたくさんいると思います。でも私は、展示会前には没頭しすぎて食べることがおろそかになったり、身体を壊したりして。そういうやり方は自分には合っていないと思うようになったんです」

佐々木さんのつくる食器は、土の味わいが生かされた落ち着いた色味で、素朴で飾り気がないが、形はすっきりと洗練されている。あたたかみがあるやさしい印象の中に、美しさが同居している。そのバランスがちょうどよかった。
瀬戸の製陶所や窯業訓練校で学び、焼きものの基礎的な知識を得て、一時期は体を壊すほど数をこなし、つくりこんできた。そうした経験があって、今の精度の高さがあるに違いない。


「その頃はこういうものがみんな好きだろうと思うもの、つまり売れそうだなというものをたくさんつくっていました。自分が嫌なものというわけではないですが、自分より他者の目を意識していたというか」
精緻な形をしている食器がある一方で、佐々木さんの最近の代表作でもある植木鉢は、より自由で、丸っこくぽてっとした形をした平たい鉢や、伸びやかに上部の広がるもの、ひょうたん型などさまざまで、どれも土偶のようなプリミティブさを感じさせる。


「以前は植木鉢なんて、という感覚がどうしても陶芸家にはあったと思うんです。最近は名だたる作家さんも植木鉢を作られていてずいぶん状況が変わりましたが。もともと私は植物が好きでした。でも陶芸を始めた頃は、なかなかいいなと思う植木鉢がなかったんです。
当時は作家さんで植木鉢を作っている方はあまりいらっしゃらなくて。食器に比べると、穴を開けた鉢では価格が低かった。生業として植木鉢をつくるのは難しいし需要もないのかなと自分用の鉢をつくる程度だったんですが、その頃に叢さんとの出会いがありました」
「叢 – Qusamura」は、広島を拠点にサボテンなどの多肉植物と鉢を組み合わせて販売するギャラリー兼ショップ。オーナーの小田康平さんは、佐々木さんの鉢を使いたいと言ってくれた。念願の植木鉢作りが仕事になるようになった。この出会いは、大きな転機になった。

「地に足のついた生き方」を求めて
以前よりも制作にあてる時間は減ったが、いま“こういうものがつくりたい”と湧き出る気持に忠実に、陶芸に向き合うことができている。
たくさんつくってたくさん売る売れっ子作家になるより、地に足をつけた暮らしから生まれる、出自のしっかりした器をつくりたい。そう方向性が変わった過程には、何があったのだろう。
学生時代はスポーツに打ち込んだ。その延長で高校や大学に進学したが、行き詰まりを感じ、一人でできる“ものづくり”を志すようになる。瀬戸の製陶所や窯業訓練校で学び、長野で陶芸教室の講師を経験した後、生まれ育った高宮町に戻ってきた。
そこで「自分の暮らしを自分の手で整える」生き方に目覚めていく。
作陶設備のある家をもつ知人の元に通っていた時のこと。
「その方がすごくクリエイティブで、毎日のようにDIYで家のあれこれをつくっていたんです。朝から「今日はごみ箱をつくる」ってインパクトドライバーを使っておしゃれなごみ箱をつくってみたり、鶏小屋がカラフルだったり。そういうのを見ていたら、私も自分の手で暮らしをちゃんとしてみたくなって」
その後、佐々木さんはなんとセルフビルドで、工房兼住まいを友人と2人で建ててしまう。 6年かかったが、まったくの素人だと考えると、その根気たるやすごい。


2階に暮らしながら家庭菜園のような畑づくりをして、馬も飼い始めた。
それでもまだ、“地に足のついた感じ”が得られなかったという。
「どこまでいってもママゴトの延長にしか感じられなくて。どうしたらもっと地に足がつくのかとずっと考えていました。食べることや土にふれることをもっとしたいなって。それが実現したのは、結婚して今の家に来てからです」
もともと夫の親戚の住居だった家には、何世代にもわたる生活の痕跡が色濃く残っていた。家の前の川の手前には自家の田んぼも畑もあり、数々の生活道具、農機具で蔵はあふれ、保存食を蓄えておくための貯蔵庫もあった。薪割りや畑仕事、パンの焼き方。生きていくための仕事を一つずつ覚えて実行できるようになるたびに、それまですっぽり空いていた心の隙間が、埋まっていく感覚を覚えた。



この土地の「土」をつかう
今は林業家のご主人が田んぼの世話をし、佐々木さんは畑を担当。夏野菜や冬野菜、小麦も大豆も栽培している。
種をまいて大地で育てた小麦や大豆が、食べることで自分の体の一部になる。自然の循環のなかに自分もあると感じ、そのサイクルに身を置くことがたまらなく「しっくり」くるという。

「そんな生活をおくっていると、やきものの土も近隣で採れたらいいなと思うようになったんです」
ある時、近所の畑が工事で大きく掘り起こされ、地面から粘土質の土が見えていた。これは使えるかもしれないと付近をウロウロしたあげく、交渉して持ち帰った。
早速こねてみて驚いた。
「石やら根っこやら混じっているのだけど、手からぶわぁって土のエネルギーが伝わってきて、素材が生きている感じがしたんです。土の力がぐいぐい伝わってくるようで、練るのが楽しくてどんどんこねました」

繊細さを要する食器に使うのは難しそうだったが、植木鉢などには使えると思った。
今の時代、お金を出せば、いくらでもいい土が買える。インターネットで購入して届く粘土は陶芸用に調整された素材なので使いやすいし、夾雑物も入っていない。
「でも四角いビニール袋に入って届く粘土を練っても、心に響くものがなくて」
それ以後、近隣で土が見つかると取りに行き、植木鉢をつくることをくりかえした。佐々木さんが陶芸用の土を求めていると知った近隣の人たちが、土が取れそうな現場を見かけると連絡をくれるようになったという。
取材で訪れた日も、近くで採れたばかりという、鮮やかな黄色の土を見せてくれた。
「同じ場所でも、土によって状態がまったく違います。細かな石でザラザラしているのもあれば、石がまったく入ってなくて、細かくてなめらかで、形も気持よく整って…という土もあるんです。ほんとに色々」

やきものにとって土はかなめだ。産地といわれる地域では、どこも陶芸に向く土や石が採れる。陶芸に適した土があれば、質のいい器ができる。質のいい器とは、「割れにくい」「汚れにくい」「量産できる」「素地に鉄分が少ない」などの条件を満たす器だと教えてくれた人がいた。
ところがいわゆる産地でない場所でも、歴史的にみれば器づくりは日本各地で行われてきた。今ほど流通の発達していない時代、かならずしもいい土が手に入らなかった頃、人びとは地元で採れる土の短所を補うように技術力でカバーし、工夫して器をつくってきたのである。
佐々木さんは、今まで花瓶や植木鉢にしか使っていなかった地元の土を、これからは食器にも使ってみたいと考えている。
「要はどれだけ手をかけられるか、なんです。採ってきた土がガチガチでも柔らかくても、土を一度しっかりと乾燥させてから砕き、水に浸して石や根っこなどの不純物を篩で濾し、水分を抜いて成形しやすい柔らかさに調整して使います。粘土として使うのは無理でも、化粧土として塗ったりかけたり釉薬の原料として使うこともできる。作業工程が多くなるのですべては無理ですが、それほど量をつくるわけではないのでできる範囲で」

自分のコントロールの及ばない域へ
「若い頃は自分の色にしたいとか、自分がイメージしたものにいかに近づけられるかを一番に考えていました。買った材料は、安定した状態に仕上がるように調整されているので、その通りに調合すれば毎回、同じ色、質感が出て、同じものがたくさん安定してつくれる。劇薬指定で手袋とマスク必須なんて材料も、めざす質感に仕上げるために使っていました」
自分で採ってきた土や灰では、出来上がりが安定しない。
「どうしようもなく思い通りにいかないこともあります。釉薬も、自宅の薪ストーブの灰を使ってつくるのですが、いろいろな木を薪にするので常に一期一会。毎回状態が違うので、毎回が違う作業になる。でもそれが楽しみでもあるんです」

畑や田んぼの中で暮らすようになって、自分がつくりたい形ありきで強制的に調整する作り方に違和感を感じるようになった。
「いい悪いじゃなくて、どっちが気持ちいいか。まわっていく感じがするか、ですかね。目の前にある、縁のあったものを生かして形にするほうが、自然にすべてがまわっていく感じで、無理がない。自然なんじゃないかなと」
それが、佐々木さんのいう“しっくりくる”ということなのだろう。
かつて日本人の間で「自然」や「文化」といった言葉は使われなかったという。どちらも日常生活のなかに溶け込むようにあたりまえに存在し、別ものとして名前をつける必要がなかったからだ。佐々木さんのものづくりも、生きること、暮らすことと一体化しているのだろう。
春になって農業が忙しくなると田畑と工房を行き来する日々。佐々木さんは土まみれになりながら「田んぼの泥だか、陶芸の土だかわからなくなる」と笑う。
古くから続く人の営みとしてのものづくりに、一周まわって新しさを感じる。
何より生活を担う手から生まれる道具の、安心感を思った。